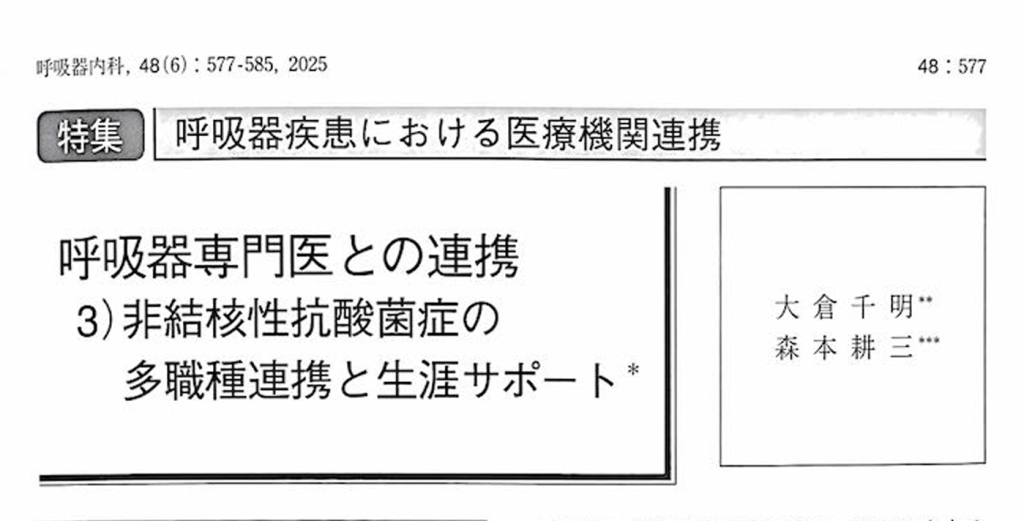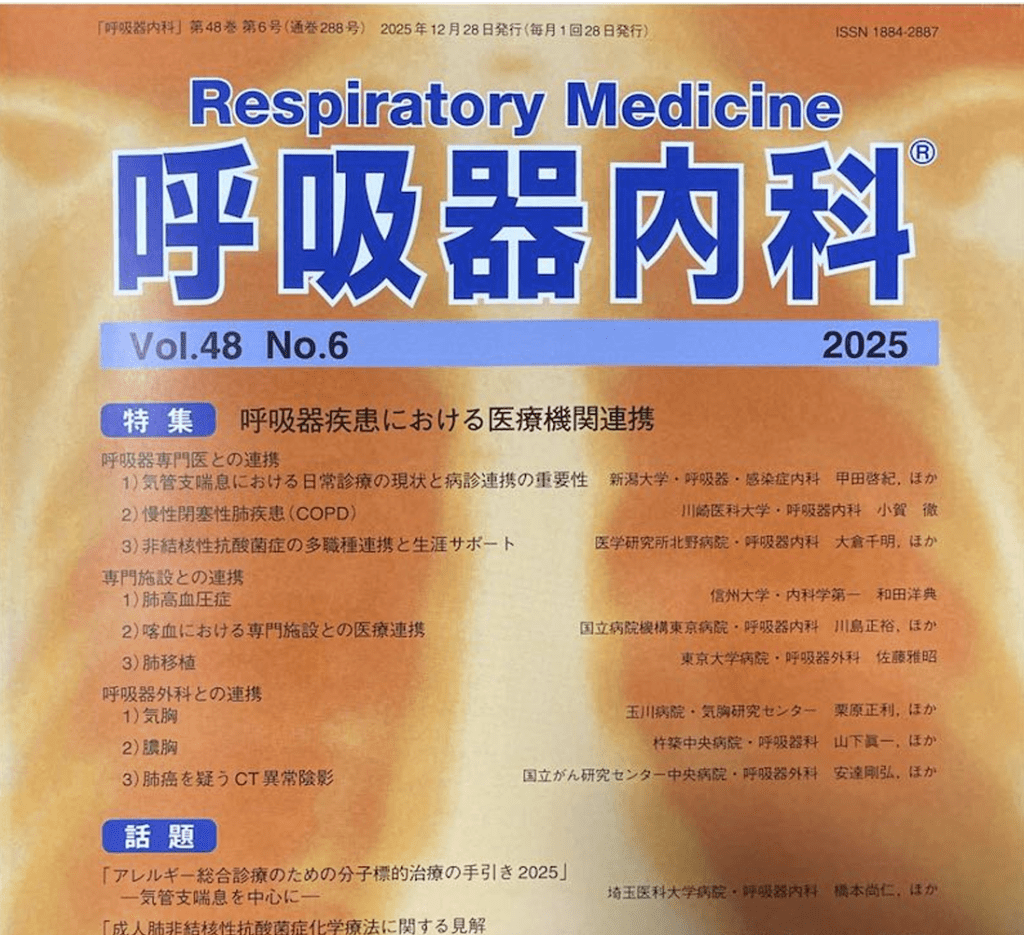RFPに代わる薬剤の探索が続きます。PROのOCをはじめて達成しましたが、将来の他の薬剤開発にも影響することを意識する必要があります。
MACの治験デザインに関してCONVERT、INS-312、ARISEなど、かなり練られていることは理解いただけると思います。

ARISE試験は、新規または再発の非空洞性MAC肺疾患患者を対象に、標準治療(アジスロマイシン+エタンブトール)へ吸入リポソーマルアミカシン(ALIS)を追加する意義を検討した国際無作為化比較試験です。6か月時点および治療終了1か月後において、ALIS併用群は対照群より高い喀痰培養陰性化率を示し、陰性化までの期間も短い傾向を示しました。また、培養陰性化とQOL-B呼吸器ドメインの改善には正の相関が認められた。新たな安全性シグナルは確認されず、新規肺MAC症における早期治療戦略としてALIS併用の可能性を示す結果といえます。
注:このARISE試験はPRO指標を決めることが目的であり、メイン試験であるENCORE結果により1stラインで使用できるかが判断されることになります。